ある日突然家族が倒れた!急な介護の始まりに戸惑っている方も多いのではないでしょうか?急な介護が必要になったとき、最初に取るべき行動を5つのステップに分けて解説していきます。
これだけは絶対に抑えておくべき!在宅介護のための5つのステップ
在宅介護はいつ、どのように始まるか予測できません。
家族の持病などがあって少し前から心の準備ができている場合もありますが、多くの人にとっては「まさか」の予測不能な事態であり、生活が大きく変わることになります。
在宅介護がスタートするにあたり、これだけは絶対に抑えてくべきというポイントを短く分かりやすくまとめましたので一緒にご確認ください。

ステップ1:まずは「現状把握」が大切
家族の介護が必要になったら、まず冷静に 本人の状態を把握すること が大切です。
「体のどこが不自由なのか?」「日常生活で何ができて、何ができないのか?」を主治医やリハビリ作業療法士さんなどに具体的に確認しましょう。
しばらく病院に入院することになる場合は、退院後の見通しを聞き出すことも重要です。
すでに退院して在宅介護が始まっている場合は、慎重に相手の状況や様子をチェックし、具体的にどんなサポートが必要なのか、何をしなければいけないのかを冷静に見極めましょう。
- 認知症の有無・程度
- 身体の機能(歩行、食事、排泄、着替えなど)
- コミュニケーション能力
- 既往歴や薬の服用状況
ステップ2:一人で抱え込まない!介護保険を申請しましょう
介護が必要と分かったら、できるだけ早く 介護保険の申請 をしましょう。これは介護サービスを受けるための第一歩です。
申請は市区町村の介護保険課で行います。本人または家族が申請できますが、おそらく本人が在宅介護になる場合は家族が申請することになるでしょう。
倒れた家族などが病院に入院している場合は、そこで申請について説明してくれることもあります。
手続きに関しては仕事で介護関係に就いている人以外は、そう何度も経験することではないので、よく分からない人の方が多いでしょう。
そのような場合は、地域包括支援センター などに相談して手続き方法を確認するのがおすすめです。プロに相談するときちんと丁寧に教えてくれて、必要なサポートが受けられます。
なお、申請後は、訪問調査と医師の意見書に基づいて「要介護認定」が出されます(通常1か月程度かかります)。
要介護度によって、利用できる介護サービスの範囲や内容が決まるので、そこで本格的に介護生活がどのようになっていくのか見通しが立ってくるでしょう。

ステップ3:ケアマネジャーと相談し、介護プランを立てよう
要介護認定を受けたら、次は ケアマネジャー に相談して、今後の介護プラン(ケアプラン)を作成してもらいます。
ケアマネジャーは、介護のプロフェッショナルとして、本人と家族の希望に合わせた最適なサービスを提案してくれます。
たとえば「デイサービスの利用」「ヘルパーによる訪問介護」「福祉用具のレンタル(ベッドや手すりなど)」「ショートステイ(短期間の施設入所)」などが一般的です。
ケアマネジャーは知識も豊富で現場経験もあるので、初めての在宅介護で戸惑っている家族に対しても、しっかりサポートしてくれます。
さまざまな状況を考慮し、介護される本人と介護する家族が暮らしていきやすいように、時間をかけて親身になって相談に乗ってくれるでしょう。
体の具合や家族の状況が変わった際は、プランの見直しや修正もしてくれます。
デイケアを受ける施設などに関しても、本人や家族の意見を尊重してくれるので、要望がある場合は遠慮せずに話をしてみてください。
長くお世話になるので、信頼関係を築いておくことが大切ですね。
ステップ4:家族での役割分担と「自分の生活」の確保
各種の申請を済ませ、介護認定もおりると、さっそく本格的に新たな生活がスタートします。
介護される人の体の状況や、意志疎通ができるかなどによって大変さは異なりますが、大切なのはまず自分自身の生活を確保することです。
家庭で在宅介護をする場合は、一人で背負い込まず、家族や親族で役割分担 を話し合いましょう。
仕事をしながら介護する場合、在宅でどこまで対応できるか、サービスをどこまで使うかを現実的に見極めることも必要です。
介護は体力的にも時間的にも、決して簡単なものではありません。仕事をフルタイムでしながらの介護は、相当な覚悟が必要になります。
遠方に住んでいる家族でも、定期的な連絡や、手続きの手伝い、費用の支援など、手伝えることはたくさんあります。
家族や親族がほんの少し関わってくれるだけでも、孤独や不安は和らぐはずです。
介護をする人が心身ともに疲弊してしまう「介護うつ」や「介護離職」も現代社会では深刻な問題になっています。
介護がこれから始まる方は、まず自分自身の生活をしっかり確保し、心身ともに余裕を持った状態を維持することが結果的に良い結果につながります。
最初から決して無理をしないこと、すべて1人で抱え込まないこと、罪悪感という観念を持たないこと、そして新しい生活に楽しみを見つけることが大切ですね。
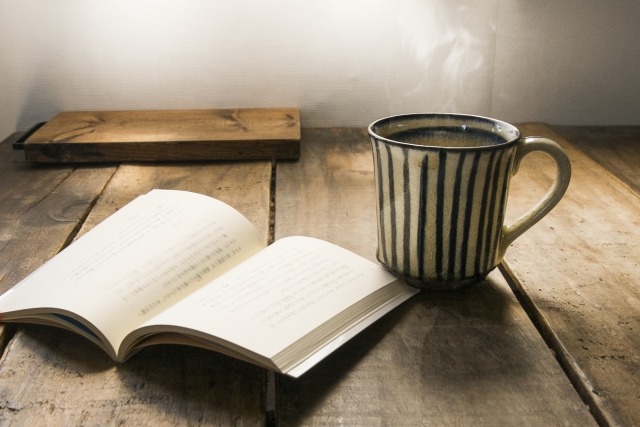
ステップ5:困ったら相談!頼れる窓口を知っておこう
介護に正解はありませんが、綺麗ごとや理想論では解決できないこともたくさんあります。
悩んだとき、疲れたとき、どうしていいか分からないときには、「相談できる場所」を知っておくことも大切です。相談できる場所の例としては次のようなものがあります。
- 地域包括支援センター
- 市区町村の福祉課・介護保険課
- 医療機関のソーシャルワーカー
- 民間の介護相談窓口
- 介護経験のある知人・家族
また、インターネット上の介護コミュニティやSNSで同じ悩みを持つ人とつながるのも、一つの支えになります。
SNSは実名で利用している人もいますが、匿名性が高いので本音を言える場所として、安らぎなることも。
介護で疲れたときに弱音を吐ける場所があり、共感してくれる人がいるのは非常に重要です。SNSは無料ですぐにアカウントも作れますので、ぜひ自分に合うコミュニティを探してみてください。
まとめ:まずは「一歩目」を踏み出すことが大切
急に始まる介護は、誰にとっても大きなストレスになります。倒れたのが大切な家族でしっかり支えていきたいと思っていても、不安や孤独を感じるのは自然なことです。
しかし、全てを完璧にこなす必要はありません。
まずは現状を把握し、専門機関に相談することから始めましょう。
「一人でなんとかしなければいけない」と思い込まず、家族や専門家の力を借りて、少しずつ対応していけば、必ず道は開けてきます。
介護は長丁場。だからこそ、最初の行動を焦らず、確実に踏み出すことが、後の安心につながります。

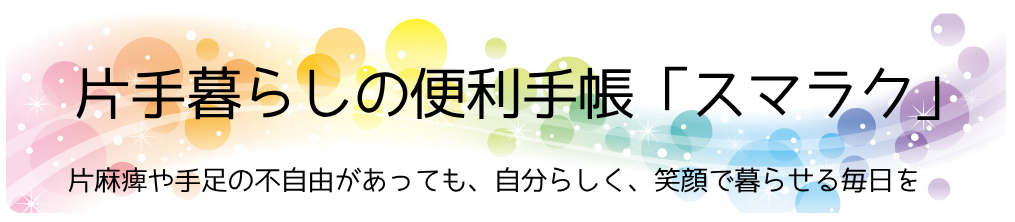



コメント